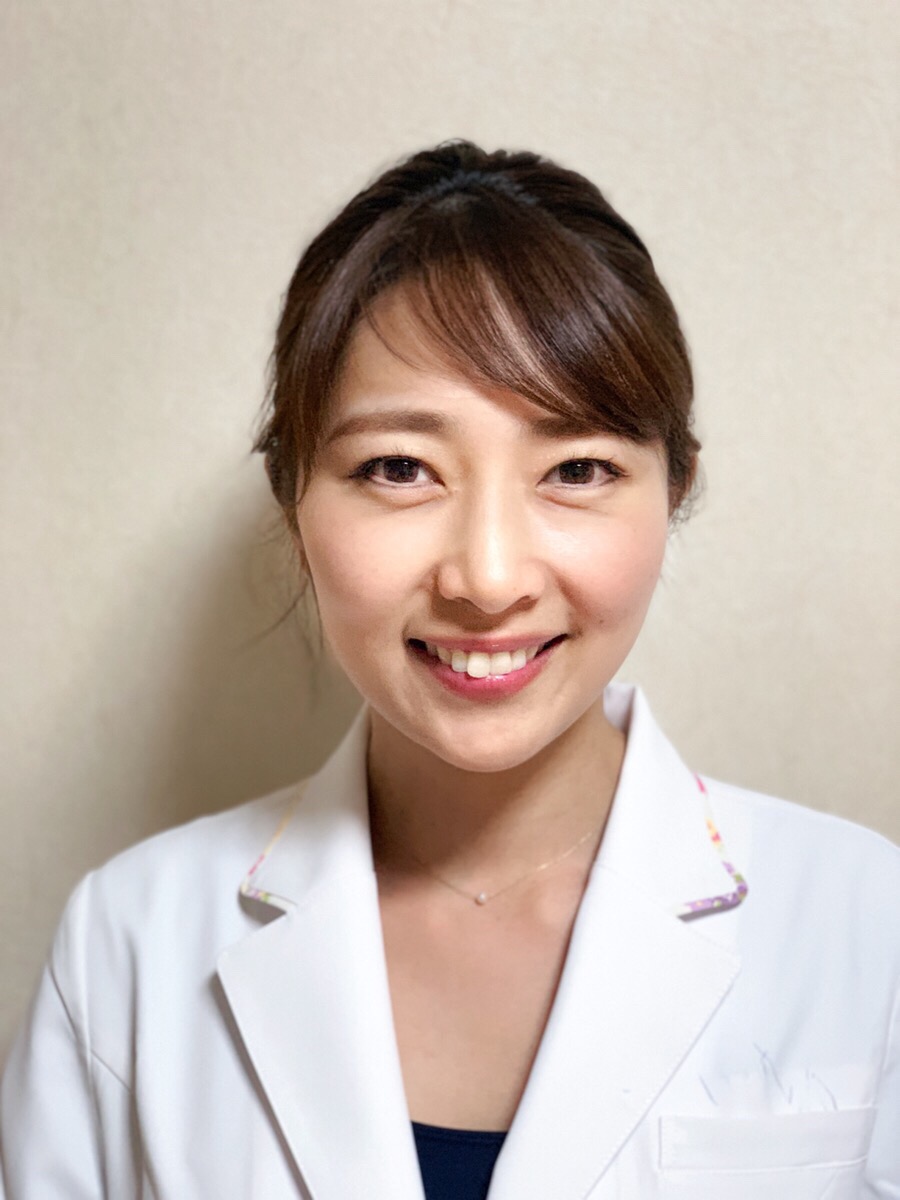【まとめ】体外受精のすすめかた
今回は体外受精を検討されている方に向けて、進め方についての解説をしていきます。
日本には様々なクリニックの種類があり、例えば自然周期を前提にした治療方針だったり、低刺激だったり、高刺激だったりと違いがありますが、全体に共通している概要部分をとなります。
1.卵巣刺激
ここでは体外受精を以下の4つのポイントに分けて紹介していきます。
- 卵巣刺激
- 受精方法
- 胚移植方法
- 胚凍結
卵巣刺激とは
卵巣刺激法とはどういうものでしょうか。
前提となる排卵のメカニズムをまずは理解しましょう。
毎月女性は排卵をしています。
排卵にあたり、およそ500個から1000個の卵子がリクルートされ、その中の一つが自然排卵をしていく、残りの約500個、1000個の卵子は体から失われてしまいます。
しかし、この失われる卵子の中にも十分に妊娠しうる卵子も含まれていると考えられており、ホルモン剤などのお薬を活用し、育てていこうというのが卵巣刺激です。
ちなみに、健康な卵子1個あたりの妊娠率は女性の年齢にもよりますが、3.5−10%程度と考えられております。
1回の採卵で、1個の卵子が得られた場合と、10個の卵子が得られた場合では、採卵あたりの妊娠率は後者の方が高くなるのはイメージが付きやすいと思います。
卵巣刺激は、女性の卵巣の予備能力や反応によって判断されることに加え、医療機関によって得意な卵巣刺激法がある場合もあります。
一般的なモデルで言えば、卵巣予備能が通常からやや高い程度であれば、積極的に卵巣刺激をして多くの卵子を得ようと考えます。
低い場合には、ホルモン剤を使用しても反応が悪い場合もあるので、低ー中程度の卵巣刺激を行います。
卵巣予備能が高いという場合は、PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)という場合もあり、卵巣刺激の副作用である卵巣過剰刺激症候群が強く出てしまうリスクがあります。
そのため、卵巣予備能を正しく測定して、あなたにあった卵巣刺激を提案してもらうことがかかせません。
2.受精方法
体外受精を進めるにあたって、卵巣刺激の次に考えるのが受精方法です。
受精方法(媒精方法ともいう)は
1)ふりかけ法
2)顕微授精(ICSI イクシー)
3)スプリット法(1と2の半分ずつ)
の選択肢が一般的です。
ふりかけ法のメリット
顕微授精に比べてコストがやや安いことが一番のメリットです。
過去に、ふりかけ法で受精障害が起こっていない方や男性不妊の要素が無い方が主な適応となります。
顕微授精
一匹の健康な精子を選び、卵子に注入していく方法です。
より確実に受精させられると考えられています。
男性不妊の要素がある方が主な適応となります。
スプリット法
はじめて体外受精に望まれるという方はこの方法となることが多いです。
男性不妊もないからとふりかけ法のみでいくと、一定の確率で受精障害というものが起こることで知られています。
せっかく得られた卵子が受精せずに治療に使用できないという状況を回避するために、この方法が取られることが一般的です。
年々男性の精液所見も低下しているという報告もあり、最近は顕微授精が急激に増加していると言われています。
なお、体外受精や顕微授精を行うことによる先天異常の増加などは報告されていません。(つまり安全ということ)
3.胚移植
体外受精を進めるにあたって、卵巣刺激・受精方法の次に考えるのが胚移植方法です。
保険診療における胚移植は
39歳以下は6回まで、40歳から42歳以下は3回までと回数制限がありますので、自分にあった胚移植方法を納得して選びたいですよね
胚移植方法の種類ととしては、2つあります。
1)新鮮胚移植
2)融解胚移植
受精卵のことを「胚」と呼びます。
胚移植の説明に入る前に、胚について少し紹介しておきます。
受精した後、受精卵は発育を続け、細胞分裂を繰り返し、変化していきます。
2−3日目の受精卵を初期胚
4−6日目の受精卵を胚盤胞と呼びます。
採卵で得られた卵子は全てが受精するわけではなく、受精後も全てが発育するわけではなくて、
初期胚まで育った胚のすべてが胚盤胞になるわけでもありません。
つまり仮に10個程度の卵子があったとしても、得られる初期胚は5-6個、胚盤胞は2-3個くらいのイメージで捉えた方がよいでしょう。
一般的に、新鮮胚移植は初期胚を使用し、融解胚移植は胚盤胞を使用することが多いです。
そのため、日本のデータで妊娠率を見ると、
新鮮胚移植<融解胚移植、という結果になっていますが、
こうした使用している胚が異なるという背景もあるので、
当然と言えば当然です。(それ以外にも妊娠率が異なる理由はたくさんあります)
新鮮胚移植
新鮮胚移植は、採卵で得た卵子、できたばかりの受精卵を採卵から2-3日後に子宮内に戻す方法です。
メリットとしては、治療開始から妊娠までの期間が短くなることが上げられます。
また、受精卵を育てる培養環境がいくら良くなったとは言え、まだ体内の環境の方が優れているという考えもあり、受精卵がうまく育たないという方にとっては、体内に早く戻すことが妊娠率を高める一因になるという考えもあります。
デメリットとしては、卵巣刺激の副作用である卵巣過剰刺激症候群になりやすいことや卵巣刺激によって、ホルモンバランスが乱れ、子宮内膜の環境が最適でない場合もあるために、妊娠率では融解胚移植の方が高いという考えもあります。
また、凍結によるダメージを胚が受けないことも上げられます。
凍結融解胚移植
融解胚移植は、採卵・受精を経て得られた受精卵を一度全て凍結します。
これを全胚凍結といいます。
採卵とは別周期に、しっかりと子宮内膜を整えた状態で胚盤胞を移植する、というのが一般的な考え方です。
メリットとしては、卵巣刺激症候群のリスクがないことや妊娠率が高いことが考えられます。
デメリットとしては、凍結による胚へのダメージが考えられること、妊娠までの期間がやや長くなる可能性があることが上げられます。
また、論文などでは、融解胚移植(厳密に言えばホルモンを薬剤で補充して行う融解胚移植)の方が、周産期の合併症や巨大児の出生が多くなるなどの報告もされています。
このほかにも、二個胚移植や二段階胚移植などもありますので、気になる方は医療機関に問い合わせてみましょう。
4.胚凍結
体外受精を進めるにあたって、避けて通れないポイントが胚凍結です。
日本では2008年に多胎妊娠の防止の観点から、単一胚移植が推奨されるようになり、そのため卵巣刺激で得た余剰の胚を凍結する必要性が出てきました。
以前は、緩慢凍結法という方法で実施をしていたものを急速に凍結することができるガラス化法というものが開発され、日本の凍結保存技術は世界トップレベルと言われるようになりました。
実際に日本の体外受精による出生児のうち、90%近くが凍結融解胚移植で生まれています。つまり一度胚を凍結しているということです。
このように胚凍結は体外受精を行う上では殆どの方が関わる技術です。
胚凍結の具体的な方法などは医療機関でお尋ねいただければ、簡単に説明してくださると思いますが、一点注意したいことが[生存率]です。
新鮮胚が良いのか凍結胚が良いのか、だけで言えば、凍結による胚へのダメージがないので、当然新鮮胚の方が良いです。
凍結を行うことで、胚にダメージがあり、その結果胚移植に使用できなくなる可能性があります。
この指標を、融解後の生存率といいます。
この指標は意外と尋ねないと知ることはできないかもしれません。
当然5個の受精卵を凍結して、4個が生存するクリニックと
5個の受精卵を凍結して、2個が生存するクリニックでは、前者の方がクォリティが高いことになります。
一般的に妊娠率という言葉が先行しており、胚移植あたり○○%が妊娠しました、という風に解釈され、
その数値が高ければクォリティが高いと思ってしまうかもしれませんが、実はこうしたプロセスが背景にはあるので、そう単純な話ではありません。
5個を胚凍結▶4個生存▶2回の胚移植で妊娠▶妊娠率は50%、残りの胚は7個
5個を胚凍結▶2個生存▶2回の胚移植で妊娠▶妊娠率は50%、残りの胚はなし
※第二子のためにはもう一度採卵から実施する必要がある
ということになります。
実際には融解後生存率が90%を超える優秀なクリニックもたくさんあります。
最近、東京都や大阪府で積極的に実施されている卵子凍結に関しても全く同じことが言えます。
何個凍結できたか、というのはあまり意味を持たず、実際に凍結した卵子が何個生存しているかが一番重要な指標になります。
医療機関をお選びいただく際のポイントとして、生存率に着目してみるのも良いでしょう。